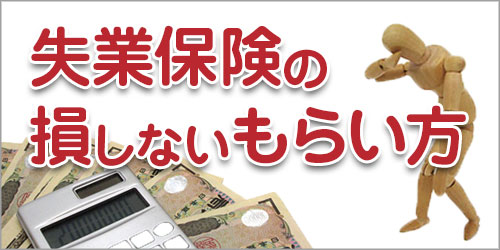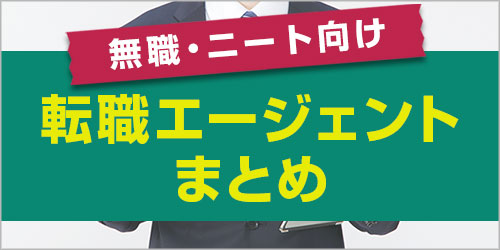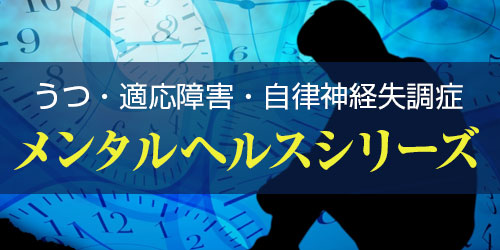国民健康保険や保育園の手続きをするときに「住民税非課税世帯の方には減免・減額措置がありますのでお問い合わせください」という案内を見たことのある人は多いのではないでしょうか。
失業して無職になったり収入が減ったときは、あなたも住民税非課税世帯になるかもしれません。
住民税非課税世帯になると、国民健康保険料が減免されたり高額療養費が減額されたり、さまざまなメリットがあります。
もし対象になったときには、これらの優遇制度を利用していきましょう。
住民税非課税世帯のメリットや、対象者となる年収や条件を分かりやすく解説します。
↓今回の内容は動画でも解説しています。
目次
住民税非課税世帯とは
住民税非課税世帯とは、世帯全員の住民税が非課税になっている世帯のことです。
住民税には所得割と均等割があり、両方が非課税になっている世帯のことを指します。
所得割は所得に比例する部分のことで、課税所得に対して市町村6%+道府県4%の合計10%が基準です。
均等割は自治体によって異なり、一般的に道府県民税1,000円、市町村民税3,000円、森林環境税1,000円の合計5,000円が基準です。
この両方が非課税になっている世帯のことを住民税非課税世帯と呼びます。
関連記事失業で住民税は減免できる!無職が知っておきたい住民税の知識
住民税非課税世帯の年収・条件
住民税非課税世帯というと低所得層のイメージがありますが、次の3種類のうちどれかに当てはまっていれば住民税非課税世帯になります。
住民税非課税世帯の条件
- 生活保護受給者
- 前年の合計所得金額が135万円以下の障がい者・未成年者・寡婦・寡夫
- 前年の合計所得金額が自治体で定める基準額以下の人
この中で3の「前年の合計所得金額が自治体で定める基準額以下の人」は、自治体よって基準額が異なります。
都心部で給与所得者の場合、年収ベースで考えると単身世帯で110万円、夫婦2人(扶養1人)の世帯で166万円、夫婦+子供1人(扶養2人)の世帯で205万7千円が目安となります。
| 単身世帯(扶養なし) | 110万円 |
|---|---|
| 夫婦2人(扶養1人) | 166万円 |
| 夫婦+子供1人(扶養2人) | 205万7千円 |
住民税非課税世帯のメリット
住民税非課税世帯には保険料や医療費の減額・免除といったメリットがあります。
中には自ら申請しないと受けられない制度もあるので、しっかりチェックしておきましょう。
国民健康保険料の減免
自治体によりますが、多くの自治体で国民健康保険料の減免を受けることができます。
制度は自治体によって異なり、だいたい2~7割の減免が受けられます。
国民健康保険料は自治体によっては高額なので、この減免の手続きはいち早くした方がいいでしょう。
住民税非課税世帯とまではいかなくても、失業や収入が激減したことで減免できる自治体もあります。
なので、収入が激減したときは一度役所へ相談に行ってみるのをおすすめします。
関連記事【国民健康保険の減免】失業したときに申請すべき減額・免除制度
ちなみに、住民税非課税世帯には年金の免除はありませんが、国民年金は前年の所得によって4分の1免除~全額免除になる制度があります。
国民年金の保険料が払えないときは、こちらも免除の申請をしておきましょう。
関連記事失業で国民年金が払えない時の免除制度 メリットと手続き方法
NHK受信料の免除
住民税非課税世帯で、世帯の中に障がい者(身体障害者・知的障害者・精神障害者)がいる場合はNHKの受診料が全額免除されます。
申請するには自治体で免除理由の証明を受けた上で、住民票と住民税非課税証明書をNHKへ郵送します。
高額療養費の負担軽減
高額療養費とは、1ヶ月の医療費の自己負担額が高額になったときに、限度額以上の自己負担分があとで払い戻される制度です。
住民税非課税世帯にはこの自己負担分が減額される優遇措置があります。
介護サービスの負担軽減
介護保険を利用して介護サービスを受ける際の自己負担上限額が、住民税非課税世帯は最大24,600円までに下がります。
さらに65歳以上は、徴収される介護保険料も減額されます。
0~2歳児の保育料無償化
幼稚園・保育所・認定こども園などに預ける際の保育料は、3~5歳児は全員無償化されています。
住民税非課税世帯になるとこれに加えて、0~2歳児の保育料も無料になります。
これにより子どもが小さいうちでも働きやすくなります。
高等教育無償化
住民税非課税世帯は所定の大学・短期大学・高等専門学校・専門学校の入学金・授業料の免除・減額が受けられます。
また、学生生活を送るための生活費となる給付型奨学金を受けることも可能です。
これらは学校の種類や世帯の収入、一人暮らしかどうかによって給付額が異なります。
その他自治体による優遇制度
自治体によってはその他にもさまざまな優遇制度があります。
- 特定健診費用の減額
- がん検診費用の免除
- 予防接種費用の免除
各自治体によって制度が異なるので、詳しくは自治体のホームページを確認してください。
また、国としても住民税非課税世帯に向けた優遇策を実施することがあります。
たとえば2024年には「1世帯あたり3万円」「子ども1人あたり2万円」が住民税非課税世帯に配られました。
バラマキとの批判もありますが、コロナ禍以降はたびたびこういった住民税非課税世帯に向けた給付金が実施されています。
このような低所得者向けの制度はニュースでも取り上げられるのでチェックしておきましょう。
-

-
【退職後の社会保険・税金】失業中の年金や健康保険 得する手続きまとめ
会社を退職したら社会保険(健康保険・年金)と税金(住民税・所得税)は自分で払わないといけません。 「退職後に何をしたらいいかよく分からない」という人のために、失業したときに行う社会保険(健康保険・年金 ...
続きを見る
住民税非課税の通知は来るのか
住民税の通知は毎年6月に送られてきます。しかし、住民税非課税の人には通知は送られてきません。
基本的に住民税が非課税になるというお知らせは来ないんです。
多くの制度は何もしなくても自動適用されますが、中には自分から申告しないと適用されない優遇措置もあります。
自分が住民税非課税の対象になっているかは、各市町村役場に問い合わせてください。
住民税非課税世帯のメリットを受けるためにも、年末調整や確定申告をしていない人は住民税の申告をしておきましょう。
住民税の申告をしておかないと自治体が昨年の所得を把握できず、住民税非課税世帯の恩恵から漏れることがあります。
関連記事無職・無収入の人は住民税の申告をしよう!市民税申告書の書き方
前年の収入が少なかったり無収入の人は、住民税の申告をすることで住民税非課税証明書が発行できるようになります。
住民税非課税証明書は、国民健康保険の減免や保育園の入園をするときに必要になってきます。
発行には200~300円の発行手数料がかかりますが、減免の額に比べたら安いものですよね。
こういった行政サービスは知らないと損をします。常にアンテナを張っておいて、収入が少ないときは有効活用してくださいね。