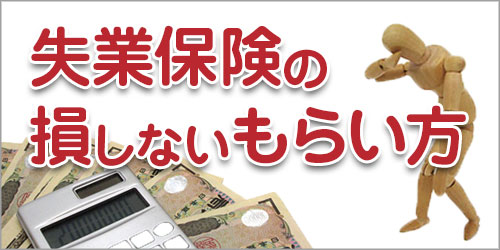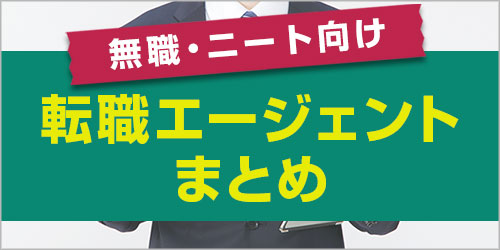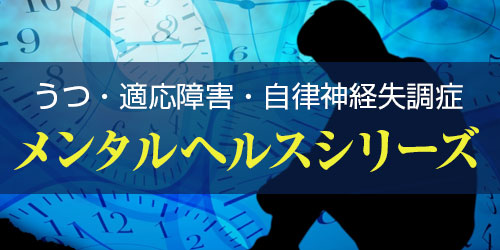先日、わが家に子供が生まれました。
僕は個人事業主としてアフィリエイトで生計を立てているので、家族が増えたからにはお金のこともちゃんと考えていかないといけません。
まず最初に立ちはだかったのは「子供は夫か妻どっちの扶養に入れるべきか?」という問題です。
わが家は夫の僕が自営業、妻が会社員。妻は現在育休中で、正社員で復帰予定です。
本来なら子供は夫の扶養に入れるのが一般的ですが、なんせ自営業は収入が不安定。毎月目まぐるしく売上が変わります。
今は僕の収入の方が多くても、妻の収入の方が多くなる可能性もありますからね。

そこで、夫が自営業・妻が会社員の場合、子供をどっちの扶養に入れるのが得かを調べてみました。
子供ができて扶養について迷ってる人は、参考にしてください。
子供の扶養の基本的な考え方
子供の扶養について考える前に、まず扶養の前提知識を知っておきましょう。
扶養には「税金の扶養」と「社会保険の扶養」があり、それぞれで意味や計算方法が違います。
「税金の扶養」は所得税・住民税の額に関わっていて、「社会保険の扶養」は健康保険料に関わっています。
ポイント
- 税金の扶養・・・所得税・住民税の額に関わる
- 社会保険の扶養・・・健康保険料に関わる
生まれた子供の扶養について考える際、「税金の扶養」については考える必要はありません。
というのも、税金の額に影響を与える「扶養控除」は16歳以上の子供が対象なので、16歳未満の段階では夫と妻どちらの扶養に入れても変わりはないのです。
(住民税については例外があるので、のちほど後述します)
なので、子供が生まれたときは「社会保険の扶養」だけ考えればOK。「どちらの健康保険で扶養に入れるか」だけを考えればいいんです。
自営業で何らかの健康保険組合に加入している人なら、そこの健康保険で子供を扶養に入れればいいでしょう。
しかし多くの人は国民健康保険に加入しているはず。
夫が国民健康保険だと、子供を扶養には入れられません。
なぜなら国民健康保険には扶養の概念自体がないからです。
夫が国民健康保険のときは
サラリーマンの場合、会社の健康保険で扶養に入れれば子供の保険料はタダになります。子供が何人いてもタダです。
しかも保険料は労使折半。本来の半分で済むんだから、サラリーマンってめちゃくちゃ優遇されてますよね。。
しかし、国民健康保険には扶養の概念そのものがありません。
つまり、子供がいれば子供の分の保険料も払わなきゃいけないんです!
ただでさえサラリーマンの2倍の保険料を払ってるのに、自営業はツライ。(>_<)
しかも国民健康保険って高齢者が多いから保険料もバカ高いんですよ。
じゃあどうすればいいかを、妻の就業形態ごとに見てみましょう。
妻が専業主婦の場合
妻が専業主婦の場合は、子供も国民健康保険に入るしかありません。
自治体によって異なりますが、子供一人分の保険料は目安として年収が500万円だと年2~3万円ぐらいでしょうか。
夫・妻・子の3人分の保険料を払わないといけないから、自営業+専業主婦の組み合わせは負担が大きいのです。
節約のためには、妻に夫の仕事を手伝ってもらうことも考えましょう。
青色申告にして妻に給与を支払えば、青色事業専従者給与として控除が使えて節税になります。
関連記事青色申告の手続きをしてきた!青色申告のメリットや始め方を解説
妻が会社員の場合
妻が会社員の場合は、妻の健康保険で子供を扶養に入れた方が保険料は安く済みます。
会社の健康保険組合なら子供の保険料はタダになるからです。
しかし、健康保険組合の扶養の基準は結構厳しかったりします。多いのは「扶養者は主たる生計者でなければいけない」というパターン。
うちの場合がこのパターンでした。僕の方が収入が多かったため、子供を妻の扶養に入れることはできませんでした。
「主たる生計者」といっても、共働きだから二人で生計を立ててるんですけどね……。

ただ、僕と妻の収入が逆転した場合は、申請すれば子供の扶養者を変えることはできます。
妻が会社員なら真っ先に妻の扶養に入れることを考えた方がいいでしょう。
会社によっては扶養手当や家族手当が出る会社もあるので、会社員のメリットは大きいです。
住民税の非課税限度額について
夫が自営業・妻が会社員の場合は子供を妻の扶養に入れた方が得ですが、ひとつ例外があります。
それは、夫の収入が少なくて住民税の非課税限度額以下になる場合です。
「税金の扶養」は16歳未満の子供には関係ありませんが、収入が住民税の非課税限度額以下なら、扶養人数に16歳未満の子供も含めていいことになっているからです。
この場合は、夫の扶養に入れると住民税が0円になります。
住民税の非課税限度額は市区町村によって違いますが、多くは以下の計算式を採用しています。
住民税の非課税限度額
たとえば子供が1人なら、
35万円×(1+1)+32万円=102万円
となり、非課税限度額は102万円です。
つまり、所得が102万円までなら住民税が非課税になるので、その場合は「税金の扶養」だけを夫側にした方が得でしょう。
関連記事住民税非課税世帯のメリット:年収や条件をわかりやすく解説
ただし、会社によっては「税金の扶養」と「社会保険の扶養」を一致させるよう言ってくる会社もあります。
社内ルールで決まってるなら仕方ないのですが、法的には「税金の扶養」と「社会保険の扶養」は夫と妻で分けても問題ありません。
住民税が非課税になるなら税金も社会保険も妻の扶養にしておいて、確定申告で「税金の扶養」だけ夫に修正するという裏技もあります。
自営業で収入が少ない年は、この裏技で住民税を非課税にすることもできるので、知っておいてください。
注意
結局わが家はこうした
というわけで、結局わが家では子供はいったん僕の扶養に入れました。というか、国民健康保険に加入しました。
保険料は増えましたが仕方ないですね。本当は妻の扶養に入れたかったんですけど。
ま、お互いの収入を見ながら、毎年どちらの扶養に入れるか決めていきたいと思います。

ちなみに扶養者の変更は自営業なら確定申告で、会社員なら年末調整でできます。
ていうか、自営業の僕は収入が下がらないよう頑張っていかないといけないですね。そっちの方が先決ですわ(笑)。